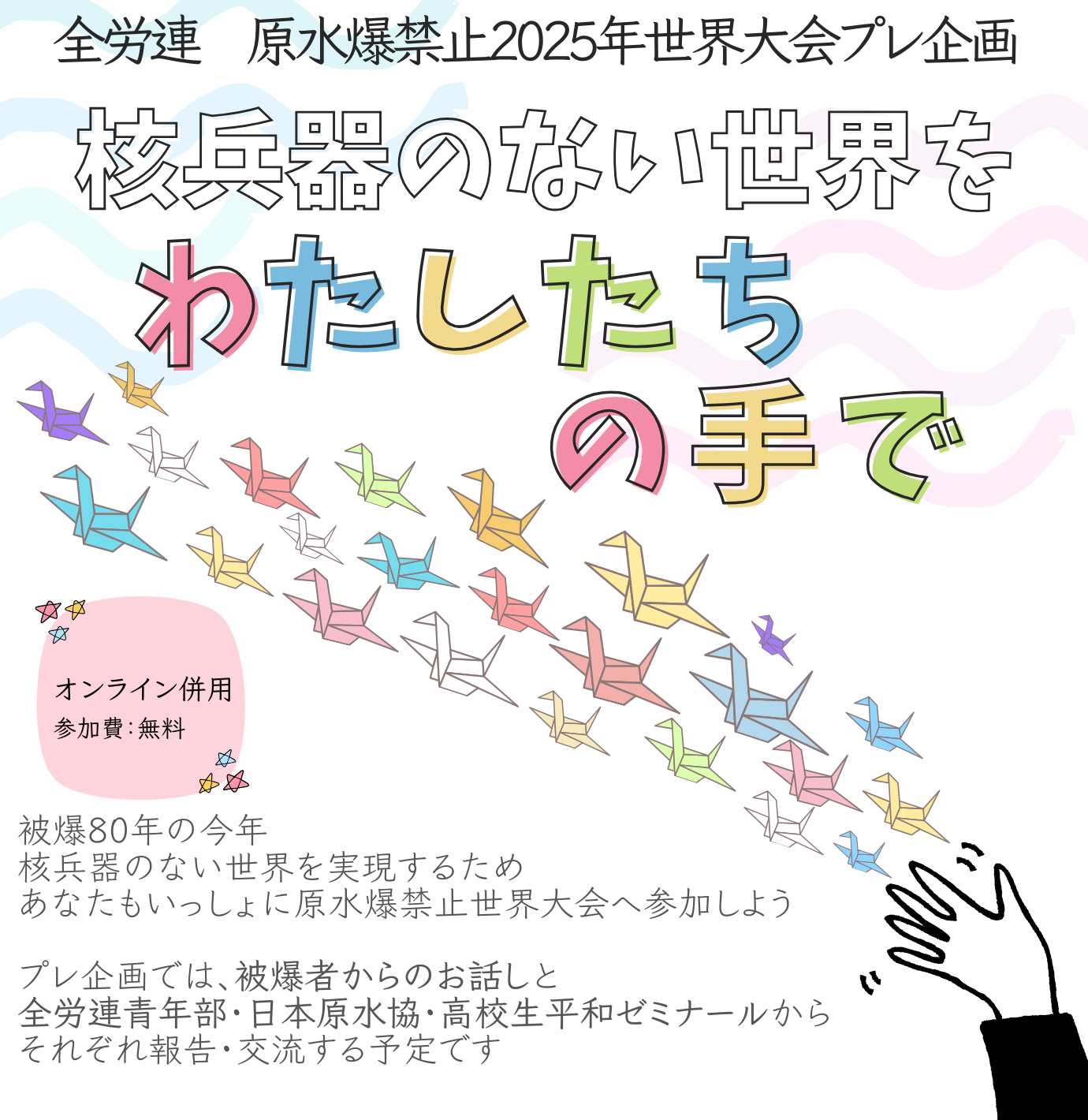新春によせて(全労連新聞583号・2025年1月)
全労連 事務局長 黒澤 幸一
「対話と学びあい」で労働者が声上げる元年に
「キャベツ一玉798円、ラーメン一杯1080円、ガソリン1リットル180円」「市内5小学校と2中学校を統合・小中一貫校になり、片道12キロの雪道をバス通学するそうだ。」新年、北海道の実家で話したことだ。
物価高騰も少子高齢化も先進国に共通してみられるが、実質賃金が四半世紀に渡り下がり続け、ドイツの1・5倍もの長時間労働が強いられる国は、日本以外にはない。女性や非正規労働者に加え、ケア労働者の低賃金が人口減少や地方経済衰退に拍車をかける。
企業の業績は過去最高を更新し続け、大企業の労働分配率は統計史上最低の38%まで低下。なのに、ストライキがあまりに少ない閉塞状況が、日本の弱点ではないか。
「企業が儲からなければ」「価格転嫁できない」との呪文が、経済全体の低迷を招き、「悪循環」が続く。
労使対等の民主主義形成こそ
では、どうしたら抜け出せるのか。労働組合主導での賃上げに変え、格差を是正し、経済の好循環をつくる。
そのためには、労使対等の原則に基づく労働条件決定のスタイルを社会通念にする以外にはない。たたかう労働組合が強くなり、労働者が「賃金を上げろ」と職場でも地域でも声を上げられるようにする。
世界の労働者がストライキでたたかっている。韓国の労働者は「大統領の戒厳令の乱用」にゼネストで立ち向かっている。民主主義の形成だ。
抑圧乗り越え怒り自覚する対話を
「抑圧される者は、怒りを覚えなくなる。抑圧する側にすら無意識に転ずる」とブラジルの教育思想家パウロ・フレイレは分析する。月刊全労連2月号「人間解放と社会変革のための対話的文化行動」野本弘幸さん(東京都立大学教授)の論文をぜひお読みいただきたい。
「労働組合で声を上げませんか」と労働者と話すところから始めよう。「対話と学びあい」を全労連の文化となるほどに広げ、仲間を増やし、声を上げたたかう元年にしようではないか。